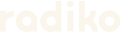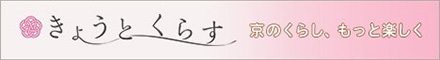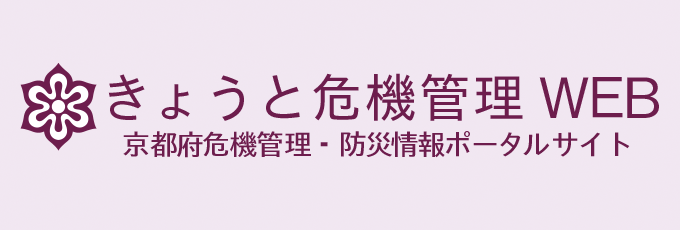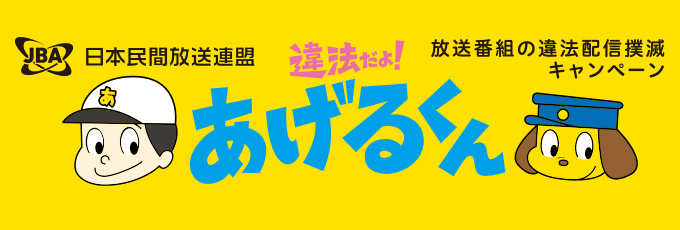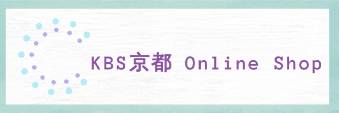ニュース
江戸時代の修験僧「円空」が日本各地を巡りながら彫り続けた仏像などの展示を通じて、信仰と布教の変遷を辿る展覧会が京都市内の美術館で始まりました。江戸時代の初めに美濃の国=現在の岐阜県に生まれた円空は、32歳の時に像を彫り始め、日本の各地を巡りながら12万体の像を彫刻したとされています。京都市下京区の美術館「えき」KYOTOできょうから始まった円空展では円空の没後330年を記念し、今に伝わる円空像を見ながら、その信仰と布教の変遷を辿ります。一見すると素朴で荒々しさを感じさせる印象ですが、ほほえみを浮かべた表情は親しみやすく、展示されている円空像には高い芸術性も感じられます。会場には円空が像を彫りはじめてから自らの悟りの境地を追い求めていた頃に制作し、強い彫りとデフォルメされた表情が個性的な十二神将像や民衆の救済を願って彫り続けていた頃に、材料の木を切り出してからわずか4日で完成させたと伝わる約180cmの像などが展示されています。展覧会では初公開となる像を含めて150体あまりを一堂に集め、円空の「祈りのかたち」を見るこの展覧会は、10月6日まで開かれています。