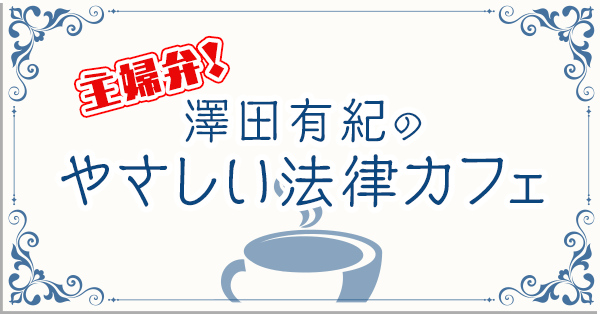10月15日のテーマは...遺言書の書き方について2
-
10月15日は、前回に引き続き、遺言書の作成についてお話いただきました。
前回は、遺言書がないと、法定相続人全員が話し合って分け方を決める必要があるという話をしました。今回は、遺言書があればどうなるかという話をします。
▼遺言書の種類
遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
どちらの形式でも法的な効力は同じで、複数作成された場合には、日付が新しい方が有効となります。ですが、自筆の場合は自分で作成するので内容があいまいで使い物にならなかったり、形式が間違っていて遺言書として無効になったりするリスクがあるので、公正証書がおすすめです。10月からは、公正証書をオンラインで作れるようにもなりました。
公正証書にしない場合でも、弁護士に内容を確認してもらう方がよいでしょう。
▼遺言書には何を書けばいい?
まずはご自身の財産をリストアップして、誰にどう分けるかを書いてください。遺産の総額がどれぐらいになるかもわかっておいてください。預貯金や有価証券は将来的に変動しますが、とりあえず現時点の額を把握してください。不動産については、建物なら固定資産税の通知書に評価額が書いてあります。土地なら毎年国税庁が発表する路線価で大体の金額を知ってください。
▼財産の配分で気を付けることは?
法定相続人が配偶者、子供、親の場合には、最低限保障される権利として「遺留分」という取り分があるので、最低限遺留分は確保しないと争いのもとになります。
生前に贈与しているといった事情があれば、その旨も遺言書に明記しておいた方がいいでしょう。
▼遺言書の書き方は?
遺言書には、誰に何を渡すのかを列挙するやり方と割合を指定するやり方があり、両方を混ぜて書くことも可能です。
(例)自宅の不動産→長男
収益物件のアパート→長女
預貯金・金融資金→3分の2を次男、3分の1を長女
その他の財産→全て長男
そのほか、仏壇やお墓の管理といった祭祀承継者を指定することもできます
最近は、「遺贈寄付」という、一部を公益団体などに寄付したいと書く方も増えています
(例)全財産の3分の2を世話を見てもらう予定の姪に、3分の1を公益団体に
このような遺言を残す場合には、必ず遺言執行者を指名してください。遺贈寄付をしたい場合には、円滑に遺産が渡せるように作成段階から弁護士に相談してください。
ご相談は【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
フリーダイヤル0120-7867-30(×2)【なやむな・みお】まで。
詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。インターネットでは24時間受付可能です。
【弁護士法人みお 京都駅前事務所】では、B型肝炎給付金説明会も行っています。まずは説明会にぜひご参加ください。
京都駅前事務所は京都駅から徒歩2分、ヨドバシカメラ向かいの京阪京都ビルの4階にあります。
KBS京都ラジオ 毎週水曜日
「となりの森谷さん」内 11:10頃 ON AIR!!
番組について
私たちにとって身近な、お金にまつわる色々な法律問題についての解決方法を「みお綜合法律事務所」の弁護士・澤田有紀先生にお伺いする“法律相談番組”です。
出演者
澤田有紀 (さわだ・あき)

兵庫県西宮市出身 大阪大学文学部英文科卒
趣味・特技 / エレクトーン演奏、ゴルフ
弁護士(主婦弁) 大阪弁護士会所属
弁護士法人みお綜合法律事務所代表
OL、エレクトーン奏者などを経て主婦に。阪神淡路大震災をきっかけに「社会の役に立つ仕事をしたい」と一念発起して司法試験の勉強を始め、平成9年司法試験に受験1回目で合格。個人及び法人の債務問題,相続・離婚などの個人の法律問題を中心に取り扱っている。
専業主婦から弁護士になった経緯については「人生を変える!3分割勉強法」(祥伝社)をご覧ください。
森谷威夫 (もりたに・たけお)

KBS京都アナウンサー。ニュースからスポーツ実況、バラエティまでマルチにこなす実力派。
リンク
番組へのメッセージ
番組へのメッセージは「番組メッセージフォーム」からお送りください。「mio@kbs.kyoto」でも受け付けています。皆さまからのメッセージをお待ちしております。